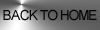「文學與影像比讀」講座之三 許鞍華(アン・ホイ) |
|
戀》談起"の中から、《欲望の翼》と《ルージュ》に関する部分を抜粋し訳を掲載します。 | |
|
改編與懐舊―由《傾城之戀》談起 ◎《阿飛正傳》的「感覚」―《欲望の翼》における「感覚」時代背景については、もしその必要があるなら、十分に調べる方が良い。時間をかけて、より多くのことを理解すべきだ。慌しく行ったのなら、出来上りも「まあ見られるが」という程度で、十分な計画と熟考を経て出来上がったものにはならない。《傾城の恋》の美術は拙劣とは言わないまでも、統一感を欠くのが問題である。先に十分調査し、一つ主となる特徴を選んで、その作品の雰囲気を作ることも大切だ。しかし時代背景を再現するには、それ以上に「感覚に訴えかける」ものを用いる事が必要だろう。「視覚的な」ものではなく。 《欲望の翼》をご覧になっただろうか?私はこの作品を見て、何故作品中の60年代が、私が経験してきた60年代と異なるのだろうと思った。(《傾城の恋》と同様)この作品でも、細部にまでこだわった、その時代を明示するものが豊富な訳ではない。しかし何故この作品は印象深く、また批判される事が無いのか?それはこの作品が「感覚に訴える」ものを多用しているからだ ではどの様な「感覚」か?第一に、間違いなく60年代にエアコンは無かった。《欲望の翼》では多くの場面で、例えばレスリーが帰宅し、その後カリーナ・ラウとふざけ合うシーンでは、扇風機が回っている。前面にあったり背景にあったり、扇風機は写っていなくても動いており、音を立てている。全シーンに「シャシャシャシャ」という音が響いている。多くの場合、耳に入る感覚は、目で見る感覚より強烈だ。これは総合的な感覚で、影響を受けた事さえ気づかない。だからこそ、扇風機という物を用いたのだろう。扇風機は、当時はあったが現在は見なくなった。また音を立てるため、動いていることが分かる。それと同時にそこに置いてあっても、それと感じない位にごく普通にあるものだ。そして作品中の「熱」を強調する効果もある・・・こういった「作用」が幾重にも重なり、時代の特色を出す効果を上げており、観客は知らず知らずに影響され、ただ場面を見ている以上の印象を受ける。大雨のシーンでも、香港の夏の印象が際立っている。 また今では炭酸飲料は多く缶入りだが、60年代には瓶が一般的だった。瓶を持って飲んでいたのだ。《欲望の翼》で、マギー・チャンが飲料を売っているシーンが多いが、「シュポッ!」と栓を抜きジュースを飲む。この情景は作品中に溶け込んでおり、特別な大道具を用いた訳でもないが、作品中の重要な部分であり、重要な道具でもある。またマギーとカリーナが言い争うシーンでは、マギーが抜き出す瓶が「カチンカチン」と音をたて、また瓶を蹴る音等も、作品に溶け合って一体となっている。音が作品の一部となり、音声上の効果、作品上の効果を上げた時、ただ作品を飾る時代背景というだけではなくなる。こういったものは、細心の注意を払って選び、鋭い目をもって、独自の視点から、どのように作品に溶け込ませれば、時代背景が作品と一つになるかを考える必要がある。実際には多くの場合、時代背景は時代背景、セリフはセリフとして考えてしまい、全てを合わせてみて、統一感や全体としてのバランスを考えることは少ない。その結果、単調な効果しかあげられず、せっかくの苦労も徒労に終る。観客は映画の全体を見ているのだ。気に入った衣装だから俳優に着せるというのでは、まとまりあるものには出来ない。 《欲望の翼》の優れた手法の3つ目は、60年代の服を選ばなかったことだ。つまり当時流行した服を着せず、全体の印象を重視している。例えば60年代にスカートのラインは「A」字型もしくは「逆A」字型が多かった。カリーナはずっと「逆A」字のスカートで出ている。マギーは「A」字型だ。さらに登場する青年は全て、髪をポマードで固めている。アンディ・ラウもトニー・レオンも、大げさなほど塗っている。実際には青年が皆、ポマードを使っていたのではない。これは観る人にある種の「時代が違う」という感覚、「60年代だ」という印象を与えるためだ。その為には服のラインを限定する方が、流行った服を多く選ぶより勝る。デザインは多すぎるほどあるが、ラインを一種にすれば統一感が生まれるのだ。服のラインは毎年変わり、現在のTシャツのラインは数年前のものとは異なる。少しでも差が有れば、何故こちらが流行りで、あちらが時代遅れか分かる。それはラインの問題だ。 手法の4つ目は、《欲望の翼》が、その時代特有の音楽を使っていることだ。音もラインも視覚的なものではなく、感覚的なものだ。作品では60年代の音楽、そのバーチャルな感じ、当時の曲アレンジや楽器を多用して、しかし服装は完全にその時代のものという訳ではない。この統一感のもつ効果は、(60年代という)オリジナルの魅力に新しい要素を加え、互いにぶつかり合い、新しい印象を与える。実際には、その中には新も旧も含まれている。 映画を撮るには、先にあらゆる要素について考えておくべきだ。要素の多くは変化し、時にはプラスに作用し、時にはマイナスに作用する。創作は運にさえ左右される。しかしこうした工夫をこらさなければ、創作とは言えず、ただあるがままに写すのみだ。私は自分が《傾城の恋》では懸命にやったものの、あるがままに写したのみだったと思う。それぞれの要素について十分に考えられていなかった。何を主に、何を副に、どのようにミックスするかというのは、視覚上の編集のレベルだ。 -----《欲望の翼》の場面放映----- このシーンで、上述のジュース瓶や服のラインが、大体は見て頂けるだろう。ウォン・カーワイはその時代において、小さくてもシンボリックな物、そして音のある物、音として効果のある物を選んでいる。注目したいのはこの作品の美術、道具、音楽、編集、演出などが一体となって、しっかりと組合わさっている事だ。撮影方法に統一感があり、全て狭角レンズを使用し、背景を曖昧にしている。背景はそこまで必要がない為だ。広角レンズを使用すれば背景も正面もはっきりするが、作品では終始背景をぼかす事で、ノスタルジックな感じを出している。はっきり見えないので、夢のような印象を受け、非常に上手くいっている。また視覚効果という点でも、色彩やライトなども、統一感がある。 一般の観客は、監督がどうやって効果を創り出すか知らないだろう。しかし、効果については感じるはずだ。《傾城の恋》ではその点を考えられていない。それぞれのシーンをどう撮るかを考え、撮影方法を統一する事で、時代背景の朧(おぼろ)な感じを出す事が出来なかった。こういう事は撮影前に良く考え、取捨選択してからかかるべきだ。 次に《ルージュ》を例にとって、原作の改編について話そう。《ルージュ》と《傾城の恋》の「字をそのまま写す」式の改編とは違う。私は自分の作品がまずいと言いに来た訳ではないが(笑)、そういう意味ではなく、例にとって論じてみたい。《ルージュ》の改編は、非常に良く出来ている。この事は原作とも関係があるが、原作がまずい為に書き換えが上手くいったのではなく、原作と改編作とは別物だ。《ルージュ》の改編が非常に巧みだという事だ。 ◎《胭脂扣》的改編 ― 《ルージュ》の改編 《ルージュ》の原作から如花と十二少の段落を取り去れば、李碧華は、あの幽霊に出会うカップルを、一幕の物語として書いたのが分かるだろう。如花と十二少については叙事詩のように、ただその中で少し、当時はどんな様子だったか描かれているのみだ。しかし、映画では如花の物語を発展させて何場ものドラマに仕立てている。例えば小説には、如花と十二少が初めて出会う場面、どのように出会ったかについて、詳しいことは書かれていない。しかし映画にはこの丸々一シーンが加えられた。そしてここから改編もしくはワン・シーンを書く時に、注意すべき事が分かる。ドラマの中には、場面設定を必要とするものがある。時代劇であれば、更に観客に時代背景を分からせるシーンが必要となる。 《ルージュ》の世界は石塘咀、妓女、花柳界であり、旧懐をそそり魅力のある場所だ。だから映画では妓院が二階建ての高い建物で、古色蒼然としているところを見せている。また如花は最初のシーンでは男装で登場するが、これは意図を持った演出だ。つまり如花は声も良く容姿端麗であることを示し、彼女が《客途秋恨》を歌う。この曲は有名で、まさに妓女と客との哀切な物語を歌ったものだ。だから如花の美声は観る者にストーリーだけでなく、背景となる音楽と場面設定をも紹介する役割を果たしている。側で楽器を演奏している者もおり、二人が初めて出会う場面を盛り上げている。これが改編だ。妓女が「琵琶仔」などとも呼ばれているが、妓女には独特の習慣やしきたりがあり、お手拭を渡してからお金を受け取る、それぞれの客の後ろに一人の少女が立ってサービスをするなど、これは花柳界でのしきたりであり、一種の文化だ。こういった風習には根拠があり、美しく、研究すれば興味深い。彼女らの話し方は昔風の広東語で、花柳界ことばもある。そういった事を、全て初めて出会う場面に盛り込んでいる。監督がこの場面を製作した時に、歌、ドラマ、背景設定の他に、どのように後につなげていくかも考えただろう。これは全て改編によって行った事で、原作で述べられているわずかな情報から、ワン・シーンを創造している。 また他に十二少が如花を訪ねるシーンがある。この時如花は明らかに暇なのに、十二少を待たせ、マージャンに行かなくちゃと言って、ずっと十二少を待たせる様に変えられている。ここでは一面、彼の誠意を描き、また妓女たちの常套手段も描いている。彼を焦らせて、簡単には手に入れられぬ様にする。非常に面白く、また優雅なシーンだ。如花が行く度、十二少は寝ていたり、帰ったかと思ったら、窓を開けてみたり・・・如花がどのように十二少を弄んでいるか、おふざけも含み、見ごたえのあるシーンだ。これは原作にはなく、原作の設定を流用している。ここから推測するに、如花と十二少のシーンは、全てこのように書かれたのだろう。 後にはお決まりだが、また美しいシーンがある。妓女が心から十二少を慕ってついていく。しかし彼の家が許さず、如花は彼の母親に会って、辛らつな言葉を投げつけられるという・・・こういったシーンでは豊かな想像力と、緻密な設計能力がなければ、如花の気持ちを観客に伝える事は出来ない。この種のストーリーは過去に何度も撮影されているが、しかし《ルージュ》では巧みに処理され、全てのシーンにおいて、その場面設計とセリフがすばらしい。 時には原作の設定の一部を新たに構成し直して、ワン・シーンに仕立てる事がある。映画では、例えば、この段では十二少の身分を言い、次のシーンでは二人の初対面を描くなど、小説の設定を改編によって、全て表現できるようになる。私はこの作業はシナリオ作成と改編において、最も難しいと思う。しかし《ルージュ》では非常に巧みだ。原作が悪いというのではなく、原作はそれほど多く書く必要は無かった。一場一場を書かなくとも、その雰囲気が出せた。 しかしもし監督がただ原作通りを撮ったなら、作品中に、これほど豊富な内容は見られなかっただろう。スタンリー・クワン監督は《ルージュ》の撮影時、モダンな現代のカップルと50年代の情侶(カップル)を対比させようと考えたそうだ。元々はそれぞれ同程度の出番があったが、編集の段階で現代のカップルは削られた。過去の情侶のドラマが美しかったからだろう。 だからアニタ・ムイとレスリー・チャンが作品の主要な部分を占めることになった。こういった出演割合の問題は、良く起こる。撮影が終ってから良し悪しが分かるからだ。もちろん成功を期待して撮るが、時には当初思ったような効果が上がらなかったり、効果を十分表現できなったりする事がある。結局効果の良い方が、メインになる。 では先にお話したシーンを見て頂き、その後また討論に移ろう。 -----《ルージュ》の場面放映-----
|
|