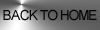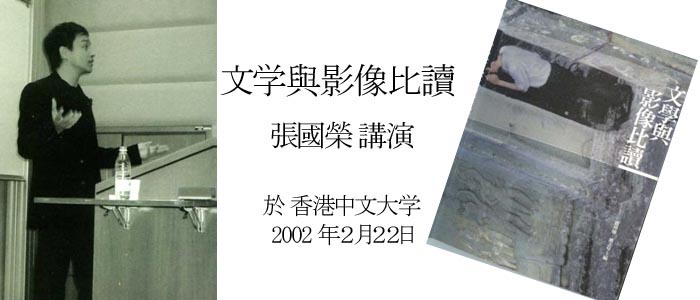
|
|
『文学與影像比讀』 盧 この著書を編纂された盧 Special thanks to Professor Lo for giving us permission to introduce her book on Leslie titled We also would like to thank the webmaster of lesliecheung.info. for her warm support in making this happen. |
|
序言 「香港文学専題・・文学與影像比讀」課程について 香港中文大学中文学科で教えて20数年、中国現代文学と創作の2科目を設けてきた。私自身は香港文学の研究に多くの時間を費やしてきたが、大学で「香港文学」課を開設したことはなかった。理由はただ一つ。資料を欠き、研究も深まっておらず、解決できない問題がまだ多くあるからだ。 2000年になり、退職を2年後に控え、私は何かが学科の教育に不足している気がしていた。そこで新しい課程「香港文学散歩」および「香港文学専題:文学與影像比讀」の開設を決めた。この2課程は一貫して伝統的な国語学、文学、文献の教育と研究を重視してきた中文学科にとっては実際のところ「らしくない」だろう。2001年「香港文学散歩」課程を設け、「遠方傾慕−雙城情結」「血脈相連−南来君臨」「本土身世−朦朧尋覓」等のテーマに基づいて作品を精読した。またそれ以外に学生を連れ出して実地の考察を行い、現場での雰囲気を味わわせたり、電影資料館で関連する時代の作品を鑑賞させたりした。このような授業は、伝統的文学を研究してきた中文学科としては前代未聞であった。2002年に開講した「香港文学専題」では、映像化された文学作品ばかりを取り上げ、研究対象とした。こういった教養課程や文化研究に近い手法も、今までの中文学科では選ばなかっただろう。 私は特にこの機会に、課程で得た経験を検証したいと思った。私がこの課程を開設する目的として強調したかったのは、現代香港文学の精読と考察を通じて、適当に読み流したり、鑑賞したりという習慣を糾すことだった。「問題を発見する」意識を持ち、問題について思索して欲しかった。また映像ばかり見ている人に、文字に戻って一字一句を読んで欲しかった。また読み慣れている人には、すでにどこにでもあふれている映像と文字との関係を考え、この二つの完全に異なるメディアの間を自由に行き来し、どちらか一方だけに偏って欲しくなかった。問題を発見して、その原因を追及し、さらに解説や解釈を加えれば、大きな喜びが得られるものだ。 当初この課程を選択する学生が100名を超えるとは予想していなかった。元々の計画では、クラス全員に指定した作品を読ませる。本も映画も、テレビ版も見せる。全ての学生が精読するように、クラスを班に分けて課題となる作品を設定する。事前に精読した作品、映像研究した作品を、後で私の授業で討論し、さらに研究すべきテーマを設定する。参考資料を加えて全員に配布し、話し合えるようにする。討論においては、文章の技巧、理論の組み立てが当然重要となる。しかし思いもかけず、学生たちは「過剰なほどに」詳細まで研究していた。私が言う「過剰」はもちろん悪い意味ではない。私が学生に与えた印象が「とても細かい」というもので、彼らもその方面に力を尽くしたのかもしれない。例えば劉以鬯の〈對倒〉を研究した班は、長・短編の文字本とテレビ版を比較し、後者が使用した音楽にはどういう意味があるのかまで討論した。また李碧華の《覇王別姫》を研究した班は、1985年の簡略版と1992年の修訂版を比較したほか、羅啓鋭のテレビ版と陳凱歌の映画版を比較し、異同の原因を細心に探り出した。他の班も文字版と映像を探し出し、微妙なカメラワークや、調度品の違いなど細部の変化を探し出した。私も気づかなかった箇所が多かった。このように精読することが、彼らの視野を狭くするか、もしくは過分に分解的にさせるかは分からない。もうこの課程を再開する機会がないので、証拠を求めようがない。 全ての作品を検討した後だが、答えを深めるべき問題がまだまだあると感じていた。もしその問いと関係のある方に解説して頂ける、もしくは交流できれば研究の成果はさらに高まるだろう。そこで講演を計画し、演技者、作者、監督に来校頂き、研究作品について学生に講演し、質問に答えて頂いた。この演技者、作者、監督と作品の間の相互解析は、学生にとって疑問の解決であり、深化でもあり、授業では得難い相互交流であり、ぶつかり合いであった。劉以鬯氏は講演するより、学生と話すほうが良いと仰ったので、形態が変わっている。 張國榮氏、伍淑賢女史、許鞍華女史、劉以鬯氏。皆、講演でも質疑応答でも、喜んで率直に自らの考えを話してくださった。こういったやり取りと交流は、学生にとっても非常に貴重な経験であった。各氏の出席のおかげで、私たちはこのような学習の機会が持て、またどの回も満足の行く結果が得られた。また講演記録を文字にして出版する事も承諾してくださった。ここで心よりお礼を申し上げたい。 盧 ■附記−追記 学生を集め、各講演者の原稿を整理しようと思っていた矢先、不吉な知らせが届いた。張國榮氏が突然亡くなったというのだ。今回の講演記録は、彼の絶唱となってしまった。校正しながら彼の話を細かく検討していると、あの日の彼の一言一動が思い出され、あたかも今、目の当たりにしているようだった。彼が一瞬のうちに身をおどらせ、滅する事のない悲劇を書いてしまうとは思いもかけなかった。香港は真摯な、傑出した俳優を失った。私は悲しみに打ちひしがれて、校正の終った原稿をしまった。 ■引子−導入 張國榮は早くも1980年に、李碧華の脚本による香港電台のテレビドラマ《我家的女人》で、景生役を演じた。その後また李碧華の小説を基にした映画《ルージュ》(1988年)および《さらばわが愛、覇王別姫》(1993年)で十二少および、程蝶衣を演じた。彼の声・姿そして演技は、忘れがたい印象を残している。今回の講座では十二少および程蝶衣という二人の人物に重点をおき、張國榮が俳優および読者と言う立場から見た二人の人物、そして《ルージュ》と《覇王別姫》の理解、さらに演じるにあたってのあれこれを語ってもらう。 |
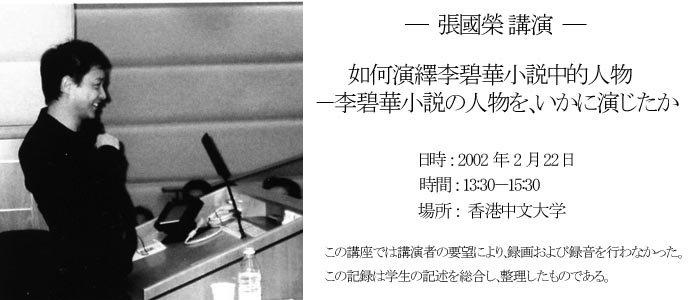
|
|
■開篇 − オープニング 私と李碧華は親友です。李碧華の作品を何作か主演しましたが、全てすばらしい作品でした!第一の作品は《我家的女人》 註1:《我家的女人》は香港電台の「歳月河山」シリーズの一つ。李碧華脚本、黄敬強監督、張敏儀プロデュースで、1980年に製作された。「第16回シカゴ国際映画祭」の金賞および、「第一回英連邦映画・テレビ祭」の銀賞を獲得している。 ■在《 《ルージュ》の十二少役には、初め鄭少秋(アダム・チェン)が選ばれていました。しかし鄭が沈殿霞(鄭の前妻)の妊娠によって辞退した為、私に話が来ました。最初に受け取った台本では、私の出番は三ページ分しかなく、セリフも全部で十数句。10日前後で撮影できる量でした。 事実《ルージュ》の原作では、十二少の重要性は遠く如花に及びません。しかし私はこの役を受け、役作りを試みました−長衫を着てどれだけ美しい立ち居振る舞いを見せられるか。人にこの役は私のために書かれたと思わせるようにと。李碧華は私の魅力に動かされ、特別に出番を増やしてくれました。また監督の關錦鵬(スタンリー・クワン)も私の撮影期間を20数日まで増やしました。そして作品は最後には、二つの異なる年代の複線形式になったのです。これも証明になるでしょう。私は魅力のある俳優なのです。作者にとって、あるいは商業的角度から言っても、私は観客にとって一定の吸引力があり、呼び込む力があり、これはまさに市場が要求しているものです。 こういった理由で、映画版の《ルージュ》では、十二少の記述は原作に比べて非常に多くなっています。だから私もこの作品で「最優秀男優賞」にノミネートされたのでしょう。 今まで演じた役の中で、個人的に最も好きなのは《ルージュ》の十二少です。監督の關錦鵬も非常に開かれた考えで撮っており、人物の感情も制約することなく描いています。この点で關錦鵬監督が私の演技を重視し、重要な役に引き上げてくれたと思います。《ルージュ》について監督が、女性の執着心を強調していると言う人がいますが、李碧華の原作がそうなっており、人物も元々その様に描かれています。 十二少の役については、実際かなり複雑でもあり、単純でもあります。彼は如花のために、豊かな身代は捨てられたが、生死の選択を迫られると弱々しく怯え、無力で、逃げようとさえします。私は基本的に彼は「色好み」で「臆病者」だと思いました。こういった人物を演じるのは挑戦です。この人はいつも「性」と「愛」に揺れていますし! そして李碧華の《ルージュ》が最も人を引きつけるのは、夢現に空虚に生きている感じ、愛情のために全てを注ぎこんでしまう感じをよく描いているからでしょう。また読む者を丹念に作り出した情調と雰囲気の中に引き引きずり込み、ストーリーの展開を追わせます。少し前、小思(盧教授のペンネーム)が李碧華の新作〈呑噬〉について教えてくれましたが、これもすばらしい作品でした。李碧華の作品は私を引きつけてやみませんし、彼女の筆になる役を演じる前に、まず役が好きになります。また《ルージュ》映画版と文字版のエンディングには違いがありますが、ここが映画監督と作者が映像と文字と言う二種類の媒体を使って、ストーリーを表現する時の手法の違いを表しています。しかしもちろん映画版の方がドラマ性が高いですし、これは必要な事でもあります。 ■如花與十二少的愛情糾結是怎樣的? −如花と十二少の愛情の複雑な関係は? 《ルージュ》の十二少が飲んだアヘンの量について、「結局は如花は死んで、彼は難を逃れて、いたずらに生き続けた。これは理屈に合わないではないか」と問う人がいます。李碧華は「十二少は豊かな家の御曹司です。幼い頃から衣食も十分足りていた。故に基礎体力といったものが妓女をしていた如花よりあった。抵抗力も強かった。」と説明しています。しかしもし十二少が死んでしまったら、《ルージュ》は劇になりません。また世の中には奇妙な事が満ち溢れています。起こりえないことはないでしょう。 劇中の「情に殉じる」筋書きは、如花がそう願って計画した毒殺です。彼女は十二少が意識が朦朧となったのを見計らってアヘンを食べさせます。本質的には「故意に騙し、殺意があった」でしょう。しかし作品の最後では、落ちぶれてまともな生活も出来ない十二少は、如花の幽霊を見て、意外にも「すまなかった」と泣いて訴えます。ここには矛盾がないでしょうか? しかし実際には、どうして十二少が如花の心を知らないことがありましょう?殺意をもっていても愛し、敬するに足る。この美女は彼のために死のうとしているのだ。また苦しみながら半世紀もの間彼を待った。しかし彼はそれほどの想いを背負いきれない。そして彼女と共に死ぬ勇気もない。ですから十二少が詫びているのは、彼が如花の真心に背いたことに対してです。それと如花が殺意を持っていたことは別に考えるべきです。なぜなら結局如花は亡くなったのに、彼は生き続けたからです! 《ルージュ》の結末について、先ほどある学生の方が、如花が歳をとり落ちぶれた十二少を見た時、彼を見捨て、ルージュの小箱まで返した事が分からないと仰いました。 あなたは恋をしたことがないのでは?だから分からないのでしょう。本当に恋愛した事のない人は、精神的にはまだ子どもです。愛情がどのように人の心に刻まれるか知らず、恋をしている時、時に複雑でまた矛盾した気持ちになる事も分からないでしょう。愛情はA+B=Cというように単純ではありません。如花が最後にルージュの小箱を十二少に返したのは、面と向かって彼との関係を断つと申し出たことで、心情的には絶交です。ルージュの小箱は、十二少が贈った愛情の証ですから、このように大切な物を付き返すと言うのは、全てが終ったこと。如花がこれほど長い間の待つ苦しみに、やっと終止符が打てるということです。 ■《覇王別姫》的結局處理 −《さらばわが愛、覇王別姫》の結末について 《さらばわが愛、覇王別姫(以下、覇王別姫)》の最後は、原作と比較すると大きく違い、奇異に感じるかもしれません。原作ではもう一人の「虞姫」である菊仙が亡くなり、覇王・段小樓が南へ渡り香港に行く。数十年を経て、年取った程蝶衣と再会します。ドーランを洗い落とし、名声もかつてのものとなった二人は、銭湯で素っ裸で出会いますが、年取った事だけで全てがあいまいになり、悲喜こもごもの感情も薄れてしまったようです!映画版では、香港行きの場面をばっさり切り、「虞姫」の役を取られた程蝶衣が舞台上で自刎し、「覇王」の段小樓がこの「女性」の現実世界での幼名を呼ぶ。その後意味ありげな笑みを浮かべ、そこで全てが終ります。 このエンディングは私と張豊毅(チョン・フォンイー)が考えました。私たちは作品の前半の製作と演技を経て、時代の荒波の中、作品で覇王が「香港へ渡る」ようにはしがたいと感じました!結局のところ「文化大革命」部分は非常に重苦しいです。そのシーンの後で、小説の通り、彼らが年を取って再会する必要はありません。これによって「ドラマ」が損なわれるでしょう。二人は互いに対する昔の愛情と以前のままの感覚で相手を思い出し、何気なく共にいれば良いと思います。 ■両個主角之間的關係 −2人の主人公の関係 私と張豊毅はずっと二つの役の間の、感情の動きに着目していました。特に程蝶衣の兄 弟子に対する愛情の変化に。はじめは蝶衣の兄弟子に対する敬慕です。半ばで兄弟子が菊仙を愛するようになっても、蝶衣は兄弟子を恋い続けます。最後には蝶衣は歳をとり、かつての様ではなくなる。しかしそれでも依然、兄弟子との間に愛情を感じている。ですから蝶衣の死には、3つの原因があると言えます。 第一に、虞姫の執着。覇王の面前で死にたいという。作品では蝶衣が虞姫であり、虞姫も蝶衣で、二人の運命は互いに重なり合っています。「覇王」はすでに力を失っており、覇王の相手を演じる「彼女」―虞姫は、もはやいつまでもこの感情を引きずっていられません。そして死ぬにしても覇王の目の前で死にたい。 第二に、蝶衣は自殺によってオリジナルの物語を完成させたいと思った。 蝶衣は夢想的な人物です。彼は舞台上で熱く生き生きと演じることを好み、また舞台で兄弟子と「覇王別姫」を演じる時にのみ、兄弟子と真の夫婦一対になりたいという願いを叶えられました。舞台は蝶衣がその夢想を実現する場所でした。ですから蝶衣が現実の生活では、彼と兄弟子はもうかつての様な親密な関係でないと気づいた時、彼はむしろ虞姫の姿で人生の幕を引く事を選び、現実に「覇王別姫」を再現しました。 第三に、歳を重ねる事が受け入れられず、蝶衣は自殺を選んだ。なぜなら彼はかつて絶世の美形であり、それで観衆を魅了してきたからです。こうしてみると分かるように、主人公二人の愛情はもともと「覇王別姫」という原作を抜け出せない運命です。ですから映画の結末では、本来の物語に帰るのが道理で、ドラマチックでしょう!また蝶衣の性格からすると、この様な愛情が受け入れられるはずがありません。覇王がすでに力を失っているのに、舞台を下りた現実世界にまでだらだらと感情を引きずるのは、耐え難いことです。現実生活では、程蝶衣はわがままに生きていますが、それゆえに「彼女」は現実が自分にとって好ましくない方向に進むのは許せません。 また私たちの理解では「別姫である虞姫」こと程蝶衣は、夢見る「女の子」です。彼女は舞台上のあの熱気あふれる演技に想い焦がれた。そしてただ舞台の上でのみ、「彼女」は本当の意味での生を得られた。ですから彼女が舞台上で死ぬのが最も自然で、最もドラマチックなエンディングなのです! 小説版の《覇王別姫》は、李碧華は同性愛というテーマで描いています。このテーマに対し、寛容で自然なことが明らかです。しかし陳凱歌(チェン・カイコー)が改編した映画版は、極端な「同性愛への恐れ」が満ち、同性愛のみが目立たないようにしてあります。 ■同性戀的話題演繹 −同性愛というテーマの演技 もしかすると私の演技は、《覇王別姫》での同性愛の解釈を、全く違ったものにしたかもしれません!同性愛について言えば、この作品が内在するテーマですが、陳凱歌の描き方は非常に抑圧的、過分に抑圧的だと感じました。中国ではこの類のテーマの扱いには敏感にならざるをえません。陳凱歌にもその苦労があった。本音は出来れば避けたかったでしょう!それも理解できます。陳監督は多方面に気を配らなければならず、彼個人が生きてきた背景もあり、作品ではああいった描き方になったのでしょう。 そのほかに作品が売れるか、公開できるかも、陳監督の制作に大いに影響したと思います。ご存知の通り、中国の政治審査は非常に厳しく、多くの作品が国内では上映禁止となっています。《覇王別姫》は取り扱いに慎重を要するテーマを扱っており、ゆえに禁止作品になりました。この作品が後にカンヌでゴールデン・パルムドール奨を獲得し、台湾で金馬奨を受賞したとしても、中国大陸では依然上映禁止なのです。しかしながら京劇発展の過程の特殊な状況を考え、舞台上では夫婦も皆、男性である事を考えれば、男性同士に特殊な感情が芽生えても、人としては自然な事だと思います。 しかし陳凱歌は作品中ではずっと、二人の男性の感情を明確に表現しませんでした。そして鞏俐(コン・リー)(菊仙を演じる)を登場させて、物語中の同性の関係とバランスを取ろうとしました。そこで映画では鞏俐の役割が大きくなっています。ですから俳優としては、私は全力で自分の役割を果たすのみでした。程蝶衣の役をよりよく演じる事、同性への躊躇いのない、変わらぬ想いを、視線や仕草で観客に伝えました。また監督の同性愛への忌避とバランスが取れるように注意する必要がありました。張豊毅も同性愛の表現には及び腰でした。例えば腰を抱きしめるシーンがありましたが、張豊毅が私の腰を抱える時、緊張のあまり全身震えていました! 個人的には、私はある役を演じる時には、先に良く選び、心の準備をします。そうすることで十分なりきることが出来るのです。実は以前にも香港電台から《覇王別姫》のテレビ版を撮影したいとのことで、程蝶衣役の依頼があったのですが、熟考の末に断りました。 何年もたって出演を引き受け、自分を完全に解き放つ事が出来ました。俳優は自分が演じる役に命を吹き込む為には、二言なく突き進むべきだと思います。俳優が異なる人物を自由に行き来できてこそ、その人物を真に活き活きと見せられるでしょう。しかし撮影の過程では、出演者の一人として私の演技は、監督の同性愛への忌避とバランスが取れなければならず、自分の能力を尽くして、最良のものを演じるのみでした。 《覇王別姫》の映画版が原作に忠実だったならば、同性愛のドラマをもっと描いたならば、同類のテーマを扱った作品の中で、私が後に出演した《ブエノスアイレス》に比べても高い地位を得たと思います。また私は演じる上で、基本的には原作の制約は考えません。俳優は開かれた心を持つべきだと思いますし、映画もまた文字から独立して存在する、開かれた空間です。俳優はそれまでとは違った演技によって、役に新たな人生を与えられます。 ■結篇3 −終わりに 講演中、学生たちは張國榮と李碧華の合作について質問を出した。 始めにある学生が「《ルージュ》と《覇王別姫》を演じる上で、原作の制約を受けたか。また彼と李碧華が親しいことで、合作に影響する事はないか?他に李碧華のどの作品を演じてみたいか?」と聞いた。前二者については、張國榮は「それはない」と答えた。彼は「李碧華は彼を思い浮かべて書くこともある」という。「映画での表現には、基本的に原作の制約は受けない。映画は文字と性質が異なって別個に存在する、開かれた空間だと考えている。俳優は開かれた心を持つべきで、自分も解放し続けるべき。自分の演技を刷新してこそ役に新しい生命を与えられる」とのこと。 その他、張國榮は「李碧華の《青蛇》が大好きで、出来るなら許仙の役をやってみたい」白蛇、青蛇と法海など主要な役について、誰が演じるべきかを尋ねると、「DODO(鄭裕玲)、鞏俐と周潤發もいい人選だ」といった。また「李碧華の作品には絶対的な物事の是非、正誤の判断がない。「同性愛」といった慎重を期する題材でも、十分「人間性」をもって描いている。もし機会があれば、李碧華の小説の最も精彩ある部分を撮ってみたい」そうだ。 別の学生が尋ねた。「映画に関する文学作品を読んだ経験はあるか?俳優として、李碧華の両作品を読んだ時、自分がその中の役を演じる事で、普通の読者の気持ちで読んだり、作品を味わったり出来ず、小説の理解に影響する事はありえるか?」張國榮は「ありえない」と言った。どんな目的であれ、彼にとって本を読むことはまず楽しみであり、その中に入り込めるようにと思い、すぐに描かれているものに引き付けられる。張國榮は《紅樓夢》を読んだ経験を例に挙げた。「細緻な描写に描き出される世界に、うっとりした」と。また「同じ作品でも、違う時期に読めば、得られるものも違うだろう」と言う。 ただ俳優として、読みながら小説の文字を映像として思い浮かべてしてしまう。これは俳優の因果な癖かも知れないといった。「文字と映像は二つの異なったメディアであり、両者はもとより別個に存在する。映画は主に光と影を使って観客にメッセージを伝えるため、本の描写のような味わいはない。だから文字から映像にする過程で、往々にして一種の「趣き」が損なわれる。文字がもつ独特の趣きが」と言う。 最後にある学生が、「中国人という民族についての見方を話してくれるよう」に言った。 しかし後で中国での撮影を経験して、中国の山河が秀麗で壮大で、人を感動させる気迫を持っていると知った。その時から中国人であることは、誇るに値すると感じるようになった。「文化大革命」が中国に及ぼした破壊と影響は、否定できないし計り知れない。しかし「文化大革命」だけで、中国全てを評価は出来ない」と言う。 ■後記 −あとがき 文化研究の角度から文学作品を分析する事は、近年の文学研究の「大勢」である。「香港文学専題・・文学與影像比讀」課程で俳優:張國榮氏、監督:許鞍華女史、小説家:伍淑賢女史、劉以鬯氏をお招きして、御本人に語って頂いた。講義を受けた学生にとって、忘れ難い経験であったと思う。そしてこの講演とインタビューが、後には何の痕跡も残らないのなら残念極まりない。そこで今回4篇のスピーチ原稿を整理して出版することとなった。この原稿は講義の記録というだけでなく、同時に香港文学研究の第一級の研究資料でもあるだろう。 記録でもあり、資料でもある。だから私たちは出来る限り正確で、誤りのないことを望んでいる。収められた原稿は、まず学生が録音や録画を起こして初稿にした。それを盧教授と私が審査・校訂し、最後に講演者自身に手を加えて頂き、出版の許可を頂いた。ただ張國榮氏が例外である。当日の講座では、氏の希望で録音も録画もしなかった。そのため張氏のスピーチは、学生の筆記を総合したものである。学生の初稿が整理できたばかりの時に張氏が逝去されたため、張氏の親族に出版の許可を頂いた。本書が首尾よく出版できたことを、特に寛大に出版を許可してくださった張國榮氏の親族、許鞍華女史、伍淑賢女史、劉以鬯氏にお礼を申し上げる。 さらに「香港文学専題・・文学與影像比讀」課程は、盧 熊志琴 2007.02.01 |